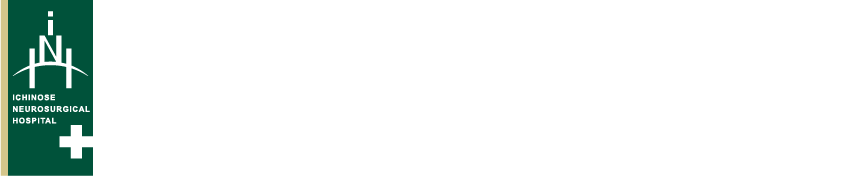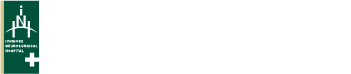健康コラム
認知症 診断と治療

「最近もの忘れが増えて心配」「家族が認知症かもしれない…」など、受診される患者さんやご家族からよく聞かれるお声です。このコラムでは、認知症ともの忘れの違い、診断の流れ、治療方法、そして予防のポイントまで、神経内科医がわかりやすく解説します。
認知症患者数の現状
認知症とは、何らかの原因で認知機能が低下し日常生活に支障をきたす状態のことです。
2024年の厚生労働省が発表したデータによると、2040年には65歳以上の高齢者の約15%(約584万人)が認知症を発症すると推定されています。
認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)も含めると、高齢者の3人に1人が罹患するとされており、誰もが認知症やMCIになり得ると言っても過言ではありません。
「もの忘れ」と「認知症」の違い
「もの忘れ」は加齢による記憶力の低下であり、必ずしも病気ではありません。物を置き忘れたり、人の名前を思い出せなかったりということは、誰もが経験することで日常生活に大きな影響を及ぼすことはありません。例えば、「眼鏡をどこに置いたかわからない」場合でも「眼鏡を置いた」ことは覚えています。
「認知症」では、ある出来事を丸ごと忘れてしまいます。先程の例でいうと「眼鏡を置いたこと」そのものを忘れ、ご本人が「眼鏡を盗られた」と思い込み、周囲とのトラブルにつながることもあります。こうなると社会生活や日常生活に支障をきたし、これが加齢によるもの忘れとの大きな違いです。
また「最近もの忘れが多くて認知症が心配」とご自身で感じ受診される方は、加齢によるもの忘れであることが多いです。逆に認知症の方は、ご自身では「大丈夫」ともの忘れの認識に乏しく、ご家族や周囲の方が心配され受診に至ることがほとんどです。
認知症の診断
まず、ご本人やご家族のお話をよくお聞きします。ご家族や周囲の方からのお話は非常に重要で、診断の大きな手がかりとなります。もちろん何か隠れている病気がないか、お身体の診察も行います。
認知機能を評価する検査には、まず長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)やミニメンタルステート検査(MMSE)などがあります。これらの検査では総合点数だけでなく、どの項目で失点したかという細かい内容も判断します。
続いて、血液検査や脳の画像検査を行います。しかし、認知症は脳の画像検査だけでは診断できません。特に初期の段階では脳の画像検査で明らかな異常がみられないこともあり、前述のような問診や検査、全てを総合して判断する必要があります。
認知症の治療
アルツハイマー型認知症では、認知機能を補助し症状を和らげることを主体とした数種類のお薬が従来から使用されています。これに加え、近年抗アミロイドβ薬という新薬が使用されるようになりました。
これらは、アルツハイマー型認知症の原因となるアミロイドβという物質を直接取り除くことを目的としており、認知機能の改善や病気の進行抑制が期待されています。しかし、使用に際しては事前にいくつかの検査が必要で、全ての患者さんに使用できるわけではありません。また、脳の腫れや出血など、注意が必要な副作用があることも知られています。
認知症の予防と生活習慣
認知症を完全に予防する方法は、残念ながら確立されていません。しかし、認知症の発生に関わる要因として生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満など)、活動低下、社会的孤立、難聴、喫煙、うつなどが知られています。
定期的な運動習慣やバランスの良い食事、社会活動への参加、人との交流や外出等は認知症を発症するリスクを低くすると言われており、こうした生活習慣の見直しは非常に重要です。また、近年の高齢化に伴い、一人暮らしの認知症患者さんも増えています。誰もが安心して過ごせる社会をつくることも、とても大切な課題です。
最後に
認知症は誰にでも起こり得る身近な病気です。「年齢のせいかも」と見過ごしてしまうこともありますが、早めに気づいて対処することが、進行を遅らせることにもつながります。
ご自身やご家族のことで気になることがあれば、どうぞお気軽に当院の神経内科までご相談ください。
一之瀬脳神経外科病院 神経内科
漆葉 怜子
0570-099-365( 24時間365日対応 )
- 受付時間
-
午前:月~土曜日 8:30~11:30
午後:月~金曜日13:00~16:00
- 休診日
- 土曜午後、日曜、祝日、お盆、
年末年始
- 面会時間
- 現在面会を禁止しております