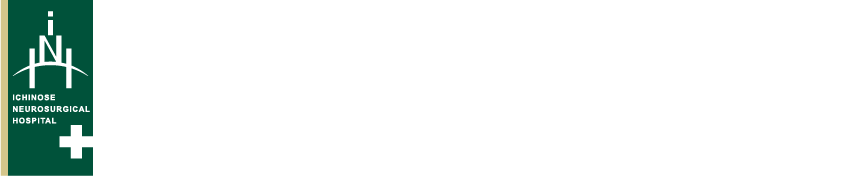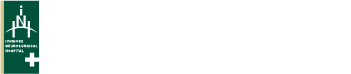健康コラム
ボトックス(ボツリヌス)治療とは…?

「ボトックス」や「ボツリヌス」という言葉を聞いて、多くの方がまず思い浮かべるのは美容医療かもしれません。しかし、実はボトックス(ボツリヌス)治療は、美容目的にとどまらず、脳神経外科領域においても重要な治療選択肢の1つとして活躍しています。
今回は、一之瀬脳神経外科病院でも実際に行っているボツリヌス治療について、わかりやすくご紹介します。
ボツリヌス菌の「毒」が薬になる?
そもそも「ボツリヌス菌」と聞くと、重篤な食中毒を起こす恐ろしい細菌というイメージを持つ方も多いでしょう。19世紀のヨーロッパでは腸詰やハムなどの保存食品、日本ではカラシレンコンによる中毒事件が有名です。また、蜂蜜や黒糖の中にも存在することがあり、腸内環境が未発達な乳幼児には与えてはいけない食品とされています。
ボツリヌス菌が作り出す毒素ボツリヌストキシンは、筋肉の神経筋接合部に作用して筋肉の過剰な収縮を抑える働きがあります。その作用は一度発現すると、神経が再生するまで持続し、微量の感染でも四肢や呼吸筋に麻痺を起こし、生命に関わることもあります。この筋肉の収縮を抑制する力を様々な疾患の治療に利用できるようにした薬剤が、ボツリヌス毒素製剤です。皆さんがよく耳にされる「ボトックス」は、このボツリヌス毒素製剤の通称のことです。
ボツリヌス治療では、ボツリヌス毒素製剤を適切に溶解して、症状の原因となっている筋肉を同定し、最適な量の薬液を注射します。安全な量を局所に利かすことで症状の緩和を図ります。
どんな症状に効く?脳神経外科での主な適応疾患
ボツリヌス治療は、脳神経外科で以下のような疾患に使用されます。
【片側顔面けいれん】
片側顔面けいれんは、顔の片側の筋肉が自分の意志とは関係なくぴくぴくとけいれんする病気です。初期はまぶたのぴくつきから始まり、徐々に頬や口元に広がっていくことが多く、進行すると顔全体が引きつるように動いてしまうこともあります。
主な原因は、顔面神経が脳の血管によって圧迫されることとされています。見た目の違和感や不快感だけでなく、日常生活にも支障をきたす場合があります。
【眼瞼けいれん】
眼瞼けいれんは、まぶたが無意識にぴくぴく動いたり、ぎゅっと閉じてしまったりする疾患で、「目が開けづらい」「まぶしく感じる」「目が疲れやすい」などの症状を伴います。
症状が進むと、自力でまぶたを開けるのが難しくなり、運転や読書、仕事にも支障をきたすことがあります。原因ははっきりとわかっていませんが、中高年以降の女性に多くみられ、まぶたを動かす筋肉の過剰な収縮が関与しています。
【痙性斜頸(けいせいしゃけい)】
痙性斜頸は、首の筋肉が異常に収縮し、頭部が不自然に傾いたり回旋したりするジストニアの一種です。姿勢を保つのが難しくなったり、痛みやこりを感じることもあり、外見上の変化が精神的な負担になることもあります。多くは成人期に発症し、原因不明のことが多いものの、中枢神経系の異常な信号伝達が関係していると考えられています。
【脳卒中後の拘縮(こうしゅく)】
脳卒中の後遺症として、手足の筋肉がこわばり、関節の動きが制限される「拘縮」が生じることがあります。これは、脳のダメージにより筋肉のコントロールが難しくなり、筋緊張が高まってしまうためです。
手が握ったまま開かない、足が突っ張って歩きにくい、関節が固まってしまうなど、日常生活に大きな支障をきたします。リハビリテーションによる機能回復が基本ですが、ボツリヌス治療を併用することで過剰な筋肉の緊張を和らげ、リハビリの効果を高めたり、介助のしやすさを向上させたりすることが期待されます。
ボツリヌス治療の流れと注意点
ボツリヌス治療は、通常外来で行われます。診察により症状の原因となっている筋肉を同定し、注射します。効果は投与後数日から1週間ほどで現れ、通常3~5ヶ月持続します。治療の性質上「症状を緩和する」治療であるため定期的な再投与が必要です。
副作用としては、効果が強く出たときに一時的に筋肉が動かしにくくなる、注射部位の赤みや出血、薬剤に対する抗体ができて効果が減弱する場合などがあるため、適切な間隔と投与量の管理が重要です。
最後に
ボツリヌス治療の最大の利点は、手術をせずに症状を軽減できる点にあります。非侵襲でありながら、症状のコントロールに大きく貢献することが期待できます。
ボツリヌス治療は、これまであきらめるしかなかった筋肉のこわばりやけいれんに対し、新たな選択肢をもたらしてくれる治療法です。
もちろん、効果が一時的であることや、副作用、保険適用の制限など注意すべき点もありますが、それらを正しく理解し、医師と相談しながら治療を継続することで、日常生活の質を大きく改善する可能性があります。気になる症状がある方や、治療に迷っている方は、一之瀬脳神経外科病院の脳神経外科外来でご相談ください。
一之瀬脳神経外科病院 脳神経外科
関口 泰之
0570-099-365( 24時間365日対応 )
- 受付時間
-
午前:月~土曜日 8:30~11:30
午後:月~金曜日13:00~16:00
- 休診日
- 土曜午後、日曜、祝日、お盆、
年末年始
- 面会時間
- 現在面会を禁止しております