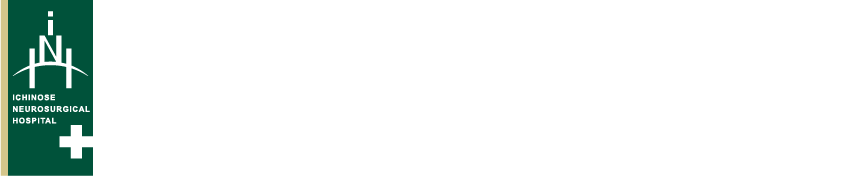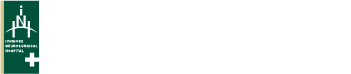健康コラム
てんかんと間違われやすい疾患

前回の健康コラムでは「てんかん」という病気について、診断や治療についてお話させていただきました。今回はてんかんと間違われやすい疾患についてお話します。
てんかんとてんかん発作
てんかんは年齢に関係なく誰もが発症しうる病気で、有病率は約1%、日本での患者数は約100万人と推定されます。てんかんは「てんかん発作」を繰り返し起こす、慢性的な脳の疾患です。簡単に言うと脳の一部や全体が勝手に興奮してしまうために、発作が起きる病気です。
「てんかん発作」は全身けいれんするというイメージが強いと思いますが、様々な種類があり、ぼーっとして反応がなくなる、どちらかの手足がギューっとしたり、がくがくする、ものが急に小さく見える、考えがまとまらなくなってうまく喋れなくなるなどといった発作もあります。これらは意識減損発作、強直発作、間代発作、視覚発作、失語発作と言われます。
同じ「てんかん」でも患者さんにより「てんかん発作」は様々ですので、それぞれの患者さんがいつもどのような発作が出るのかを知ることが重要です。その上で最も適した薬(抗てんかん発作薬)を選んで内服してもらいます。
てんかんと間違われやすい疾患
てんかん発作と間違われやすい疾患は、急性症候性発作、失神、心因性非てんかん発作、過呼吸やパニック発作、小児では熱性けいれん、軽症胃腸炎関連けいれんなどが挙げられます。
いずれも意識を失うことがあるために、てんかんと間違われやすい病気なのですが、今回は①急性症候性発作、②失神、③心因性非てんかん発作について説明してみようと思います。
①急性症候性発作
急性症候性発作は脳卒中や頭部外傷、アルコール中毒、脳外科手術後などの出来事の1週間以内に主にけいれん発作が生じる疾患です。簡単にいうと、突然の出来事で脳がびっくりして興奮するために、けいれん発作が起きます。この発作は突然の出来事に誘発されて起きる発作ですので、その出来事がなくなれば(時間が経てば)発作は起きなくなります。そのため基本的にてんかんの薬を飲む必要性はありません。一方、てんかんはそのようなイベントがなくてもいつでも発作が起きえますので、発作を抑えるための薬の内服が必要になります。
②失神
失神は、意識を失い倒れる疾患ですが、急に生じる全般的な脳血流低下が原因となります。学校で校長先生の長い話を聞いているときにバタンと倒れる、そんなイメージです。
失神は神経調節性失神、起立性低血圧、心原性失神に分けられます。60%が神経調節性失神、起立性低血圧と心原性失神がそれぞれ10%程度と言われています。
神経調節性失神は、痛み、排尿・排便、長時間の立位・座位などが誘引となることがあります。
起立性低血圧は、高齢者に多く、糖尿病、食後、血圧降下薬などの薬剤により生じやすいと言われています。
心原性失神は、不整脈や器質性心疾患が原因となります。失神は立位で起こることが多く、顔面蒼白や冷や汗などがでることがあり、意識消失の時間は短く、意識は急に回復します。
てんかんは失神と違い、体位とは関係なく発作が起こり、意識消失は長く、意識は徐々に回復することが一般的です。失神はどのような状況でどうなったかを詳しく聞くことで診断できることが多いですが、失神でも約15%~40%がけいれんを伴うことが知られており、この場合てんかんとの鑑別がより難しくなります。
③心因性非てんかん発作
心因性非てんかん発作は、心理的葛藤が原因となり、運動、感覚、認知が自己コントロールできなくなる疾患です。一言で言えば、心が原因でてんかんのような発作を起こしてしまう疾患です。
心的トラウマなどの心理的な葛藤がその原因となるのですが、本人や周囲の人も心理的な問題を自覚していないことも多くあります。以前は「偽発作」と言われていましたが、本人がわざと発作を起こしているわけではありませんので、現在では心因性非てんかん発作、精神科領域では解離(転換)性障害と言われています。
ちなみにここで言う「転換」とは解決できない問題や葛藤により生じた「心の葛藤」が症状として転換されて出現することを意味します。心因性非てんかん発作は精神科での対応や、心理的なサポートがとても重要となる疾患です。
このように、①急性症候性発作、②失神、③心因性非てんかん発作はいずれも「意識を失ってけいれんすることがある」ため、てんかんと間違われやすい疾患です。世界的に見てもてんかんの治療をされている中の2~3割がてんかんではないのにてんかんと誤診されていると言われています。その多くが不十分な問診と脳波の誤判定が原因です。
てんかんと診断するには大きな責任が生じます。それは診断した時点で、その患者さんには一生てんかんという病気と向き合ってもらい、薬を飲み続けて頂く必要性があることとほぼ同じだからです。
実際の診療では、てんかんかもしれないけど他の疾患かもしれないと悩むこともしばしばあります。その時にはどうしたらいいでしょうか?詳細に話を聞いても、脳波やMRIなどでもはっきりしなければ、治療をせずに経過を見ます。てんかんと確実に言えるか、それに等しい状況でなければ、てんかんと診断せず、薬も処方せず経過を見ていくことも大切なことになります。
おわりに
今回はてんかんと間違われやすい疾患についてお話してみました。てんかんを疑う症状が出た場合でも、てんかん以外の疾患の可能性がないかも考える必要性があります。
てんかん外来では、てんかんと診断する時には、どのようなタイプのてんかんか、てんかんの原因は何か、どのような治療が適切か、今後の見通しなども説明するように心掛けております。
てんかんは診断や治療が難しい疾患です。もしお困りの患者さんがおられたら、お気軽に相談してください。
次回のコラムでは「てんかんの啓発活動」をテーマにお届けします。一之瀬脳神経外科病院の健康コラム、今後もご期待ください!
一之瀬脳神経外科病院 てんかん外来
信州大学医学部附属病院 てんかんセンター
金谷 康平
0570-099-365( 24時間365日対応 )
- 受付時間
-
午前:月~土曜日 8:30~11:30
午後:月~金曜日13:00~16:00
- 休診日
- 土曜午後、日曜、祝日、お盆、
年末年始
- 面会時間
- 現在面会を禁止しております